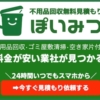おせち料理の意味と由来、それぞれの料理に込められた願いを知って新年を迎えよう
新年を迎えるにあたって、欠かせないものといえば「おせち料理」。
でも、それぞれの料理にどんな意味が込められているか、知っていますか?
この記事では、おせち料理の意味や由来、種類、そして込められた願いについて詳しく解説します。
さらに、料亭監修の本格おせちが購入できる「匠本舗」の情報もご紹介します。おせちの準備に役立つ情報が満載なので、ぜひ最後まで読んでみてください。
おせち料理とは?その意味と由来

おせち料理は、正月に食べられる日本の伝統料理です。
歳神様をお迎えし、一年の幸福を祈願するため、新年におせち料理をいただきます。
「おせち」という言葉は、本来「御節供(おせちく)」を略したもので、季節の変わり目に行われる節句の際に神様にお供えした料理を指していました。
時代とともに、節句の中でも最も重要な正月の料理を指す言葉として定着しました。
めでたいことを重ねるという意味を持つ「重箱」に詰められているのも特徴です。
おせち料理の種類と込められた願い
おせち料理には、様々な種類があり、それぞれに縁起の良い意味が込められています。
例えば、黒豆は「まめまめしく健康に過ごせるように」、数の子は「子孫繁栄」、田作り(ごまめ)は「五穀豊穣」、紅白かまぼこは「紅白でおめでたい」、伊達巻は「華やかさ、文化の発展」、栗きんとんは「金運上昇」、昆布巻きは「よろこぶ」など、新年の願いが込められています。
三段重?五段重?重箱の段数に込められた意味
おせち料理を詰める重箱は、一般的に三段重、五段重が多いですが、地域や家庭によっては四段重を使用するところもあります。
段数が増えるほど豪華になり、縁起が良いとされています。
三段重は「天地人」、五段重は「五大」に由来するとも言われています。また、四段重は「死」を連想させるため、避ける地域もあります。
正月料理とおせち料理の違い
おせち料理は正月の三が日に食べる保存性の高い料理を指し、雑煮やお汁粉など、正月に食べる料理全般を正月料理と呼びます。
つまり、おせち料理は正月料理の一部と言えます。おせちは、正月の間、台所仕事を休んで歳神様をおもてなしするために、日持ちのするものが多く作られています。
おせち料理を美味しく食べるコツ、保存方法
おせち料理は冷蔵保存が基本です。
食べる際は、それぞれの料理に適した温度に戻してから食べるとより美味しくいただけます。
例えば、かまぼこなどは常温に戻してから、煮物などは少し温めてから食べるのがおすすめです。
また、数の子など塩分の強い料理は、食べ過ぎに注意しましょう。
そろそろおせちの準備を…でも、手作りは大変…そんなあなたにおすすめ!
年末が近づくと、おせちの準備が頭をよぎりますよね。でも、手作りとなると、たくさんの品数を用意するのは大変…時間もかかるし、食材の買い出しも一苦労。ましてや、初めて作る方にとっては、ハードルが高いと感じてしまうかもしれません。
そこでおすすめしたいのが、料亭監修の本格おせちを通販で購入するという方法です。
手軽に美味しいおせちが手に入るだけでなく、プロの技が光る美しい盛り付けも魅力。
忙しい年末年始を、ちょっと贅沢に、そして楽に過ごしたい方にはぴったりです。
匠本舗の料亭おせちで、新年を華やかに彩りませんか?
数ある通販おせちの中でも、特におすすめしたいのが「匠本舗」の料亭おせち。
全国の有名料亭・名店と提携し、匠の技が光る本格おせちを販売しています。448万個以上の販売実績と94%以上の顧客満足度(日本マーケティングリサーチ機構調べ おせち通販人気No.1)が、その人気の高さを物語っています。
匠本舗のおせちは、種類も豊富。監修料亭は26屋号、50種類以上、75万個以上のおせちを販売予定なので、きっとあなたの好みに合う一品が見つかるはずです。
さらに、早期割引「早割り」を実施中!9月30日までの早割第1弾、10月31日までの早割第2弾、そして12月10日までの早割第3弾と、早く注文するほどお得に購入できます。
まとめ
おせち料理は、日本の伝統的な正月料理であり、それぞれの料理に込められた意味や由来を知ることで、より一層新年を楽しく迎えることができます。
手作りも良いですが、匠本舗のような料亭監修のおせちを通販で購入するのもおすすめです。おせち料理の種類、保存方法、そして匠本舗のおせち情報も参考に、素敵な新年をお過ごしください。